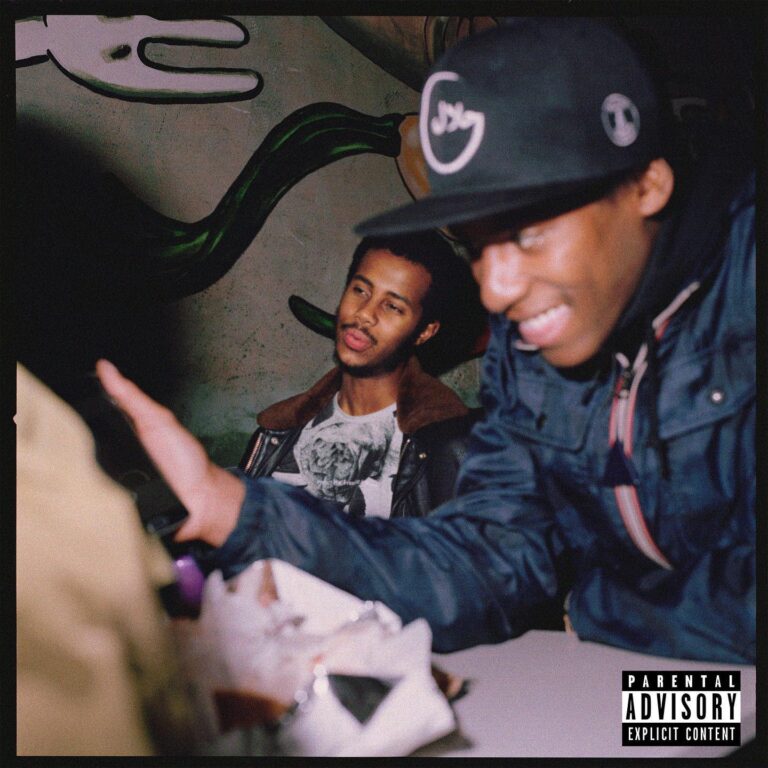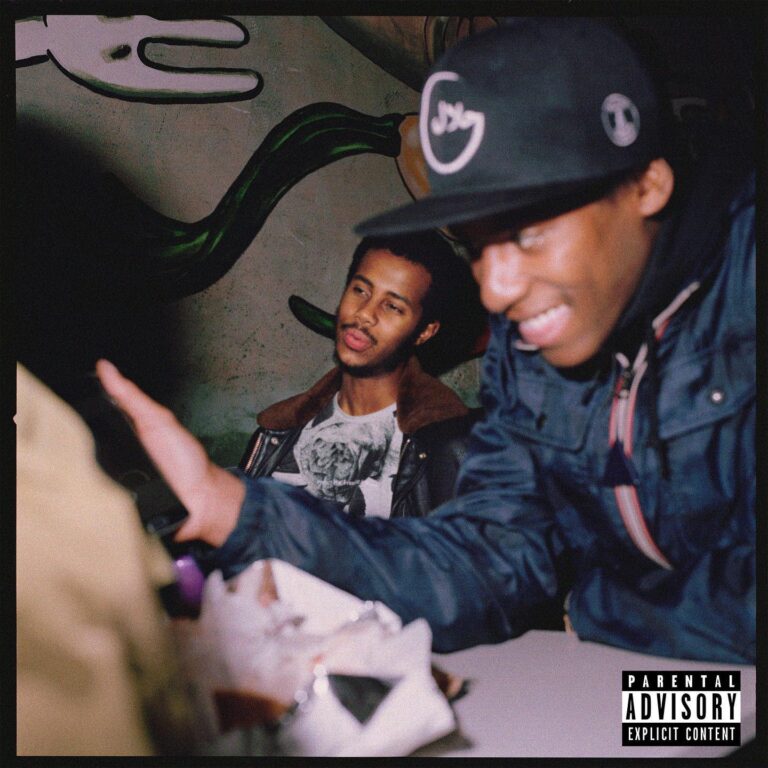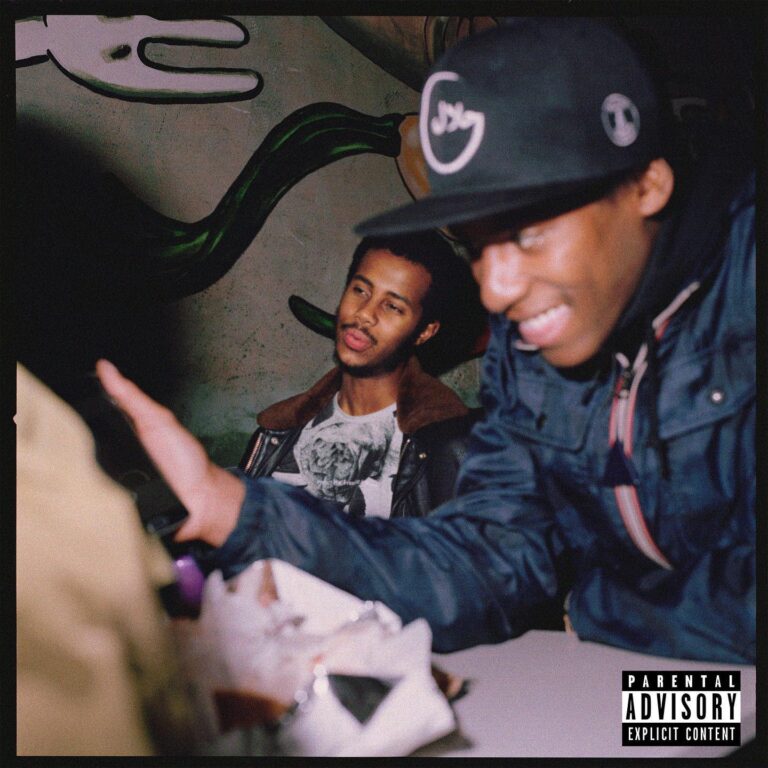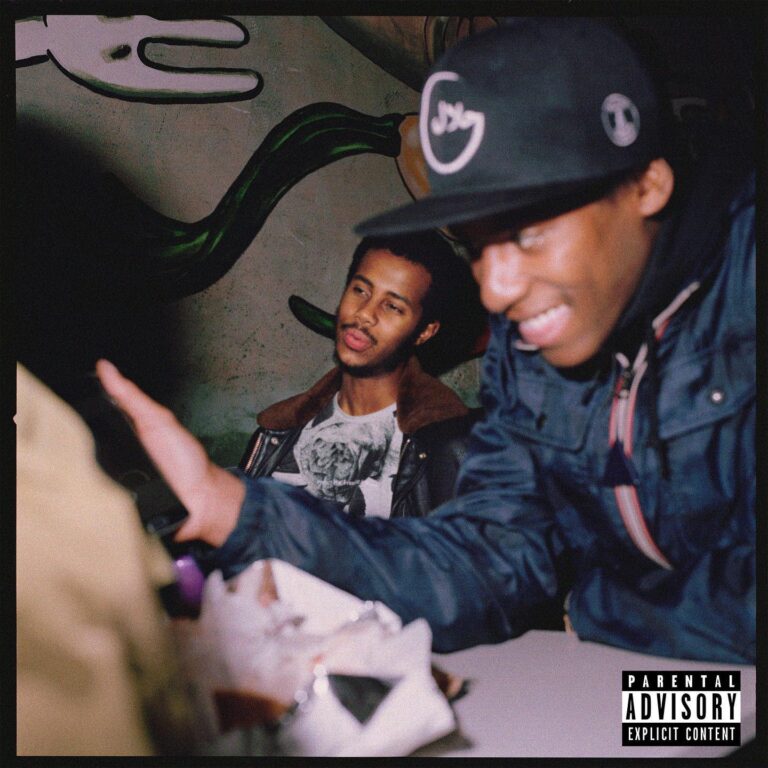Music Video
March 28, 2021
ブラッド・オレンジの音楽がカラッとした夏の陽気を誰しもに思い起こさせるかはともかく、少なくとも日本に住んでいる筆者にとって、彼の作品は真夏日ではないが半袖のシャツを着ている、5月か6月、または猛暑シーズンを超えた9月末あたりの、ちょうどいい気温の夜風にあたりながら聴きたい音楽である。それは、デヴ・ハインズの透き通った歌声のせいか、はたまた快楽的であり、官能性をも湛えるムードとサウンドのせいか。あるいは、2019年にリリースされた『Angel’s Pulse』のアルバムジャケットの、気怠くも涼しげな夏のイメージに引っ張られているのかもしれない。
 ALBUM COVER (ANGEL’S PULSE)
ALBUM COVER (ANGEL’S PULSE)
ロンドン出身のデヴ・ハインズのサウンドの引き出しは、彼の作品が大枠で括られるようなR&Bだけでなく、イギリスのポップス、バンドミュージックから、アメリカのヒップホップ、カントリーにまで連なる。
一方で、彼の書く歌詞は、断片的で抽象的な表現が多いながらも、時には、自身のセクシャル、あるいは黒人であることによる、苦しい差別や偏見に関するモチーフ、または暴力にさらされた記憶を綴る。サウンドのある種の浮遊感に対して、厳しい現実と、内容の面で非常にラディカルな接続を試みていることは、傑作『Negro Swan』を聞いてみてもより切実に感じられるだろう。そういった無国籍感のあるサウンドの中に感じられる悲しみや切なさも(しかし、ここで語られているものはこのような言葉で簡単に消費できるものではないことは頭の隅に置きつつ)、センチメンタルな気分に浸りたい涼しい夜に接続してしまう一因かもしれない。
そんな彼の音楽が、イタリアのひと夏の青春を描いたドラマ『僕らのままで We Are Who We Are』にて、ルカ・グアダニーノ監督の世界観に接続したのは、あらゆる意味で納得だった。オリジナルの映画から大胆に脚色し、主人公たちを音楽業界の人間に変換したジャック・ドレ―監督による1968年の映画『太陽が知っている』のリメイク作『胸騒ぎのシチリア』。あるいは音楽にスフィアン・スティーブンスを起用した『君の名前で僕を呼んで』、またはトム・ヨークを起用した『サスペリア』。これまでもグアダニーノの監督作品は、様々なタイプの現代音楽と密接にコネクトしてきた。
そもそも、映画史的に見ても、ミケランジェロ・アントニオーニやダリオ・アルジェントをはじめ、イタリア映画作家とその時代の音楽作家や文化のコラボレーションには非常にエキサイティングな歴史があるが、彼もまたその延長線上にいる一人なのかもしれない。
また、これらのグアダニーノの作品が、ヨーロッパを舞台にしながらも、外からやってきた人々を描いているということも重要だろう。それにより彼の作品では、イタリア映画、ないしヨーロッパ映画という枠を飛び越え、横断的なキャスティングと、アーティストとのコラボレーションが堂々と行われてきた。外から国にやってきた人々の物語。そして、勿論イタリアの米軍基地を舞台にした『僕らのままで We Are Who We Are』もまさにそんな作品なのである。
イタリアの街キオッジャの米軍基地で14歳の夏を過ごすことになったニューヨークの少年フレイザーと、その土地に住む少女ケイトリンを中心に、多感な青春の日々を切り取る今作では、デヴ・ハインズの音楽だけでなく、ラップミュージックをはじめとして様々な音楽が起用されるのも特徴的だ(因みにケイトリンの父親役でキッドカディが出演していたりもする)。いかにもヨーロッパ映画的な、モダンな形式で切り取られたキオッジャの美しい景色に、例えばカニエ・ウエスト,リック・ロスの「Devil In A New Dress」が鳴らされるマジック。こういったラップミュージックが解放的な夏の景色に合致する気持ちよさは、ある種の映像的な快楽とも言えるかもしれない。
快楽と言えば、エピソード的には第4話の恐ろしいほどの快楽的な感覚は忘れがたい。例えば『君の名前で僕を呼んで』を見た者ならば、ザ・サイケデリック・ファーズの「Love My Way」に乗せて煌びやかに踊るティモシー・シャラメの運動を忘れられないはずだ。この第4話は、端的に言ってこのシーンの瞬間的な、または運動的なときめきと快楽が50分続く作品であるといってもいい。主人公たちが他人の家に侵入しパーティーをする一晩。そこで、メロウなダンスチューンとして流されるフランク・オーシャン「NIKE」の使い方も新鮮である。
さらに、第1話におけるチャンス・ザ・ラッパー「Same Drugs」の使い方も印象的だ。今回は、チャンスがやさしく囁くような箇所が劇中で使われる。
“ Don’t forget the happy thoughts
幸せな気持ちを忘れないで
All you need is happy thoughts
きみに必要なのはそれだけだから
The past tense, past bed time
あの頃のベッドの時間に
Way back then when everything we read was real
俺たちが読んだものはすべてが真実で
And everything we said rhymed
全てで韻を踏んでいた
Wide eyed kids being kids. Why did you stop?
子供のままでいるのをなぜやめてしまったの?
What did you do to your hair?
髪型も変わってしまったし
Where did you go to end up right back here?
どうせここに戻ってくるのに、いったいどこへ行ってたの?
When did you start to forget how to fly?
いつから飛び方を忘れはじめたの? ”
– Same Drugs (2016)
この歌詞が、青春期のセンチメンタルな有限性と純真さにおいて図らずもこのドラマと合致してしまうような使われ方である。『We Are Who We Are』というタイトルにも切実に響いてきそうな歌詞でもあるだろう。
 HBO
HBO
このような既存曲のユニークな使われ方もさることながら、やはり、デヴ・ハインズによるスコアは突出しているだろう。例えば、劇中におけるストップモーション、あるいはスローモーションに、唐突に鳴らされる重いシンセの音は、その瞬間を特別なものとして閉じ込めるような効果を発揮する。あるいは、周りの景色が流されていくような、情感あふれるピアノのメロディも忘れがたい。
デヴ・ハインズ自身はすでに『QUEEN & SLIM』など、映画音楽の仕事も経験済みだが、グアダニーノ作品との親和性は当然のように高い。グアダニーノ作品における、官能性、そしてどことなく感じ取れるセンチメンタルな、あるいはメランコリックな情感は、前述したように彼の音楽作品も湛えている部分である。例えば、グアダニーノが撮ったスフィアン・スティーブンス「Tell me you love me」のミュージックビデオにおける身体の捉え方とメランコリックな情感は、表層的なイメージだけでは、寧ろブラッドオレンジの曲世界に近いものすら連想もさせる(ただし、勿論冬の季節をモチーフにしているところで、また違ったスフィアンらしい抽象性と意味性を獲得している作品でもある)。
また、第5話においては、主人公のフレイザーがデヴ・ハインズについて言及するシーンさえある。今作の、セクシャル、国籍、そして人間的なアイデンティティに関するテーマは、デヴ・ハインズ自身の物語や音楽にも呼応し、より彼の存在がドラマの中に染み込んでいく。
まるで、クラシック音楽とポップミュージックとの、折衷的な今作のスコアに関しては、作曲家ジョン・アダムスの影響も大きい。彼の曲自体も今作で数曲流されると同時に、ルカ・グアダニーノの作品としては『ミラノ 愛に生きる』にも音楽で参加していたアダムスだが、デヴ・ハインズ自身もインタビューにて、彼のファンであることを公言している。グアダニーノの作品にクラシック音楽がかかる意外性はないが、そういった音楽と、アダムスの音楽に影響を受けているであろうデヴ・ハインズによるスコア、そして前述したラップをはじめとする、現代のポップミュージックがミックスされ流されると、見ている我々も、その音の混在する様に巻き込まれ、宙に浮いているような、またはフリーダムな感覚にすらなるのではないだろうか。
「イタリアの米軍基地」というと、距離的な遠さもあり、まるで別世界の生活を見ているような感覚に陥るかもしれないが、同時に、劇中の彼らがふらつく、学校や海辺、映画館やスーパーマーケットは、我々の住んでいる日常にも存在するもののはずだ。しかし、それがどうしてもこの世のものではないような、特別なものに映ってしまう。まさにそんな感覚の映像化なのである。
有限なモラトリアムの儚さを彩るデヴ・ハインズによる魅惑的なスコアと多彩な現代音楽の数々に乗せ、「自分たちはいったい何者であるのか」という、結論などいつ出るのかもわからない人生の普遍的な問いをめぐる、異国の地でのひと夏の痛々しくも美しい冒険へ、音楽好きの方々にも是非足を運んでいただきたい。『僕らのままで We Are Who We Are』は、スターチャンネルEXにて毎週木曜日に配信中だ。
Writer : 市川タツキ
RELATED POSTS
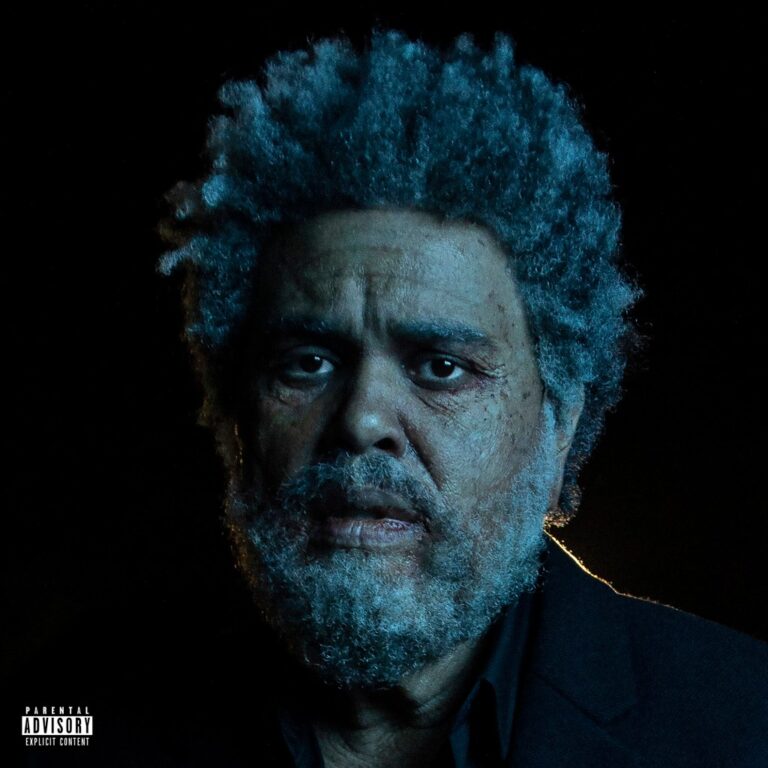

NEWS



FEATURE
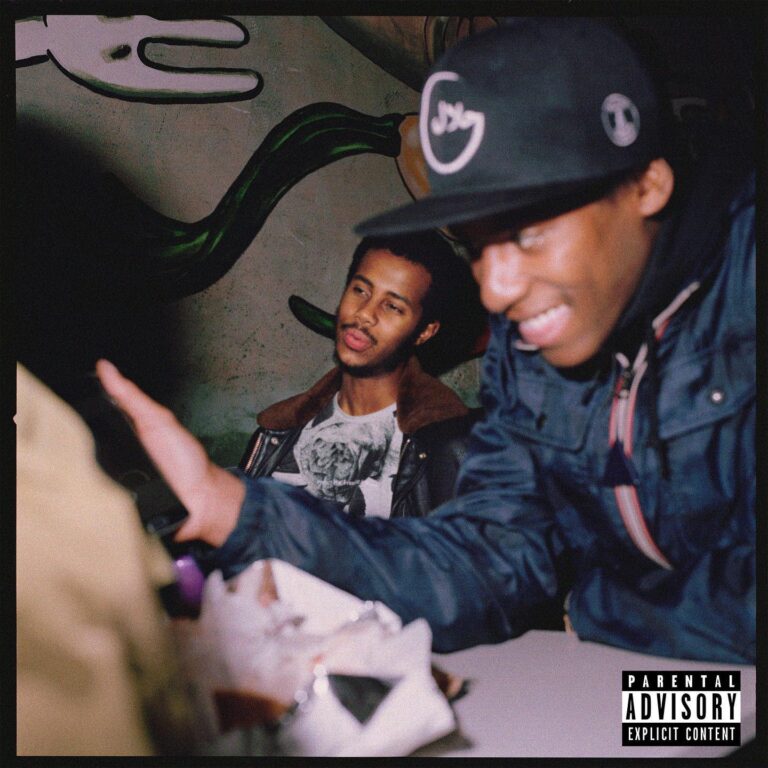

LATEST LYRICS