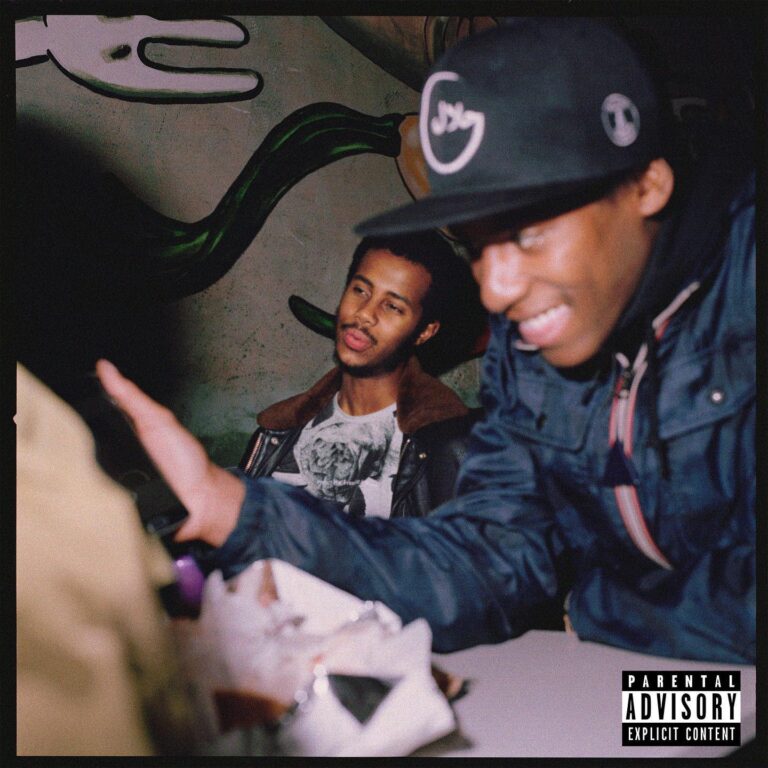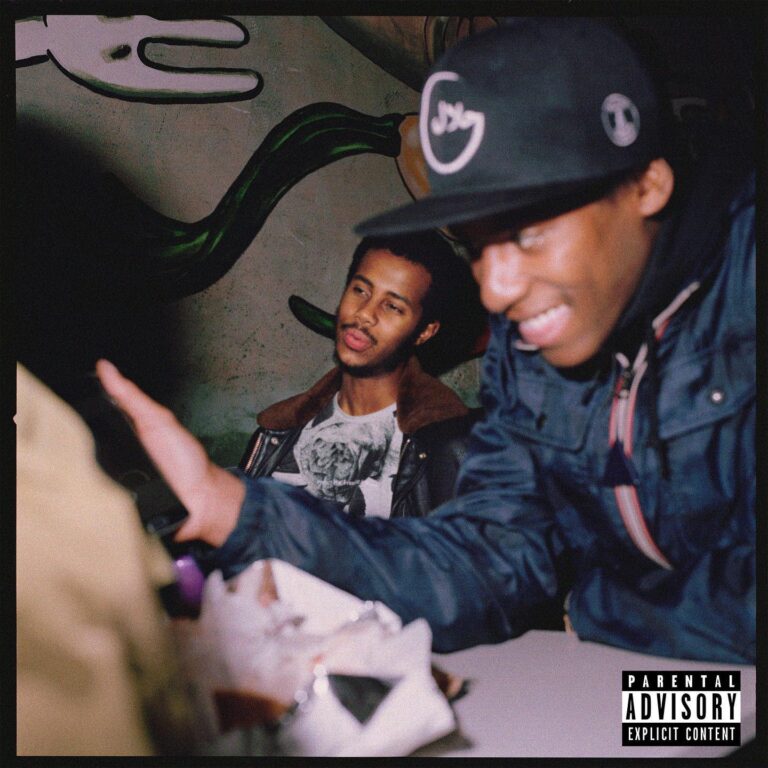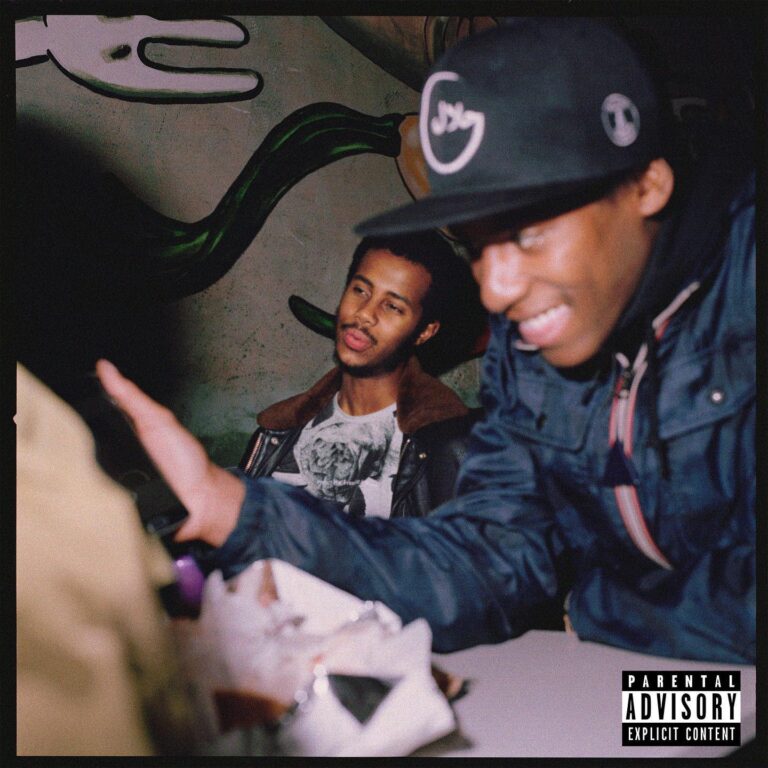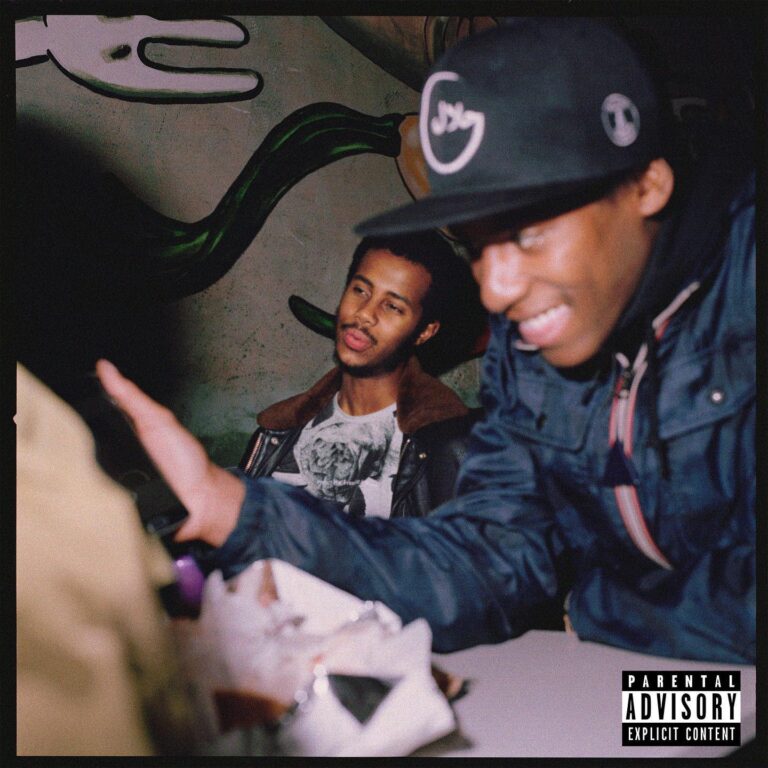A24
July 18, 2020
日本では2017年に公開し、第89回アカデミー賞で作品賞をはじめ数々の賞に輝いた映画『ムーンライト』はボリス・ガーディナ―の1973年の楽曲「Every Ni**** Is A Star」が流れるところから始まる。1974年の同名の映画のサウンドトラックとして制作されたこの曲は、2015年のケンドリック・ラマ―の名アルバム『To Pimp A Butterfly』の冒頭でも同様にサンプリングされている。黒人コミュニティの内省的テーマを語った、映画とアルバムという2つの優れたアート作品の共通点である。
さらに、黒人であり、同性愛者である主人公の少年期から成人期までを捉えた『ムーンライト』の物語世界に感動したフランク・オーシャンは、まるで自身の人生や曲世界と重なるような本作を絶賛し、A24の公式サイトから出ている『ムーンライト』のスクリーンプレイブックに序文を寄せている。このように、映画の劇中で使われている音楽の歌詞とシーンのリンクだけではなく、アーティストの世界観と映画の世界観が深いところまでお互い影響し合っていくような関係性は、近年アート作品においてさらに増えてきたといってもいいだろう。
そんな中、そういった形の作品のここ数年の集大成であるようにさえ見える映画が7月10日に公開された。それが『WAVES』である。
『ムーンライト』と同じくフロリダを舞台にした今作は、厳格な父親、義理の母、レスリングチームに所属している優秀な高校生の兄タイラー、そして妹エミリーの、ある黒人の家族を中心に、起こってしまった悲劇とそこからの破滅、そして再生の物語を語る。
すべての要素が繊細で綿密に作られた今作は監督自身も様々なインタビューで公言しているように、劇中で流れる曲世界と映画の物語世界のシンクロが特徴的であり、最も重要な部分の一つとしてある。今回の記事では、映画全体を様々な視点から掘り下げつつ、それぞれの演出がどういった形で成され、アーティストの曲の世界観とどのように映画が重なり合っていくかを読み解いていこうと思う。
今作の監督のトレイ・エドワード・シュルツは今作が長編映画3本目。家族内のギスギスとしたコミュニケーションを描いた人間ドラマ『クリシャ』でデビューし、さらに、ホラー映画『イット・カムズ・アット・ナイト』で頭角を現し今作に至る。その作風は一本一本全く違うが、家族という主題をネガティブな側面含めて映画化しているところに共通性を見出せる。今作の特徴である幻想的な撮影、視覚的な表現はシュルツ監督がカメラアシスタントとして現場に参加していた、映画作家テレンス・マリック[i]の作品からも強い影響が見て取れる。
一方で今作の幻想的で美しさと繊細さを湛える映像は、その時々のエモーションによって刺激的でパラノイア的な側面も垣間見える。そういったシーンではカメラがせわしなく動き、さらにはスクリーンサイズを変え、素早いカット割りで魅せていく。
しかし、今作で最も強い個性を放っているのはやはり音と色彩であるだろう。まさしくエンドロールでアラバマシェイクスの「Sounds and Color」という曲が流れるように、今作は「音と色の映画」そのものであるといえる。赤や青など、画面の中で様々に変化する色調は、空の色や街のライトなど、カメラに取り込まれる光によっても時に美しく、時にまがまがしく映える。視覚的な美しさという意味では前半における主人公タイラーと恋人アレクシスの海でのシーン、まがまがしさという意味では、中盤のホームパーティーにタイラーが車で向かうシーンが最も顕著だろう。それぞれ、日暮れ時の空の色と光、どぎつい色彩を浴びせる照明が、画面内のムードを演出する。
一方で音の演出も巧みである。映画が始まり、劇中で観客が耳にする最初の音はある人の呼吸音ではなかっただろうか。そしてその後、ファーストシーンとして自転車をこぐ少女の姿が映され、その呼吸音が彼女から発せられた音だということが明かされる。このシーンは物語が終わった映画のラストショットにもまた戻ってくる。そして、エンドロールが音楽とともに終わり、再び冒頭に聞いたような呼吸音が鳴り、映画は終わる。呼吸と呼吸の間、生命力の象徴ともいえるこの音の間で今回の物語は展開されるところに、生きることについて、人生についての物語であることが集約される。
このようにこの映画は細かい音に至るまで、円環や反復の構造をとっており、計算しつくされていることがわかる。さらに、今回のために手掛けられたオリジナルスコアを、ナイン・インチ・ネイルズ[ii]のメンバーであり、近年だと『ソーシャルネットワーク』をはじめとする一連のデヴィッド・フィンチャー監督の作品や、HBOドラマ『ウォッチメン』のスコアを担当したトレント・レズナーとアッティカス・ロスが務める。
日本では冬に公開されるピクサーの最新作『ソウルフル・ワールド』の音楽も手掛ける注目の映画音楽作家の二人だが、彼らのスコアもこの映画の物語世界に強度を与えている大きな要素だろう。
このように、この映画の幻想的な世界観を作り上げている要素は様々にある。そして、前述した巧みな音の演出の中で、このような映画の世界観に、劇中使われている様々な音楽たちも重なり合っていくのだ。
この映画で流れる、豪華アーティストの数々の楽曲は、ただただBGMとして平坦に流れるのではなく、基本的には主人公たちが聴いている曲として劇中に存在する。それにより、劇中の彼らが、どのような音楽やアーティストに魅了されているかという、直接的に、彼らの心情を楽曲が代弁する説得力が発生する。主人公タイラーの部屋にカニエ・ウェストの『The Life of Pablo』のポスターが貼ってあるのも、劇中での登場人物と密接な音楽の存在を示しているだろう(そういえば、このアルバムの最初のタイトル案も、アルバム内のトラックからとった「WAVES」であった)。
さらに今作は、曲が流れるといっても、そこで切り取られる部分や、音量が上がり歌詞がはっきりと聞こえてくる部分など、「どこの部分を聴かせるか」を意識的に演出している。これらは、もっとも曲中で主人公の心境とシンクロする部分を切り取るためでもあるが、同時に、劇中で流す音楽も「音」として取り込もうとする試みにも見えた。
映画の中で流れる曲はどうしても曲自体の印象が強く、曲そのものとして「その場に存在してしまう一つのモノ」になることが多いが、この映画では、曲そのものを音としても映像の中に溶け込ませ、聴覚的に主人公のエモーションを演出する効果が出ている。
例えば、序盤に主人公のタイラーと彼女のアレクシスが車を走らせながら大音量で流すアニマル・コレクティブの「FloriDada」。20世紀の芸術思想「ダダイスム」をモチーフにフロリダとその人々をトロピカルなムードのサウンドで歌ったこの曲は大音量で切り取られるブリッジに重なる、“FloriDada”と繰り返すコーラスにより、この作品の舞台の力強い宣言にも聞こえる。
あるいは、後半でエミリーと彼氏のルークの最初のロードトリップのシーンに被さるチャンス・ザ・ラッパー「How Great」。宗教的なモチーフを歌ったこの曲は、ゴスペルとラップソングの本格的な融合がなされている。この曲を車でかけるルークは「ここからが良いんだよ」とゴスペル部分からチャンス・ザ・ラッパーのラップに映るところで音量を上げ、それが彼らのロードトリップのモンタージュと重なる。映画後半でふさぎ込んでたエミリーの心情がこの旅と彼によって開かれていくという様が、この曲を通して描かれる。
さらに、音楽使いという意味ではこの映画のハイライトの一つであろうH.E.Rの「Focus」とタイラー・ザ・クリエイターの「IFHY」が流れる場面にも言及しておきたい。
主人公タイラーのジェットコースター的な状況と感情の変化を、メロディアスなH.E.Rの歌声から、ノイジーなほど音量を上げて打ち付けるように流れる「IFHY」の変化で表す一連のシーンは、一部屋のなかで一人の感情を映すシーンでありながら劇的な印象を与える。前の「Focus」が「愛する人に振り向いてほしい」という曲に対して、後の「IFHY」がタイトルの時点で「I Fucking Hate You」の略だということも、このシーンを見た人なら納得の選曲であるだろう。
このように、音量や曲の切り取りも含めた音の演出が周到にされながら、劇中流れる音楽はほかにも場面の登場人物の状況や感情に呼応する。例えば後半でエミリーが、恋人のルークが運転する車に乗り、窓から顔を出しながら夜の空気を感じる場面で流れるSZAの「Pretty Little Birds」。何度たたかれても復活し、美しい姿で飛ぶ不死鳥をモチーフにしたこの曲は、この映画の後半のエミリーの物語の「再生」というテーマに重なって聞こえる。
さらに、前半で、タイラーが病院でMRIの検査を受けるところで流れるエイサップ・ロッキーの「LVL」。タイラーによって重要な結果をもたらす、検査のシーンで流れるこの曲のタイトルははレベルという意味であり、人生におけるレベルの浮き沈みを示している。順風満帆な時もあれば最悪の時もあるということだ。これは、波が高い時もあれば低い時もあるという「人生の波」という言葉で、人生の浮き沈みを示したこの映画のタイトル『WAVES』にも通づる。
そして、監督自身も様々なインタビューで語っている通り、この映画に最も強いインスピレーションを与えているアーティストの一人であるフランク・オーシャンの楽曲もタイトルテーマに重なる。彼のアルバム『Endless』から劇中流れる「Rushes」もこの映画のタイトルの「人生の波」に通ずるような、人間関係、恋人関係の波を描いたものだ。元々、ほろ苦いラブソングの多いフランク・オーシャンの楽曲群ではあるが、この「Rushes」が流れるのはタイラーと恋人のアレクシスが、海の中で抱擁し合うシーンである。恋人との関係の終わりも感じさせるこの曲は、この映画のタイトルテーマと呼応するとともに、このシーンにおいては、後のタイラーとアレクシスの関係に関する残酷な展開も予見する。
“ Oh and it’s so cloudy
Running showers and the mist so fly
Enough time to know, know nothing at all
Oh I see the lines, there’s two lines(walls)
You’ll live a life anew ” – Rushes by Frank Ocean
彼の曲が使われたシーンでもう一つ印象的なのは「Seigfried」が流れる場面だろう。この曲も劇中の登場人物が聴いている曲として登場する(それどころか、このシーンでははっきりとエミリーのiPodに表示されたフランク・オーシャンのアルバム『Blonde』のジャケが見える)。
この曲は、後半でエミリーとルークがある決断をし、長距離の旅に出るところで流れる。フランク自身の苦悩と失恋の記憶が語られるこの曲は、パートナーとの関係に関するフランク自身の苦い決断も描かれる。
そんなこの曲から、愛するパートナー同士であるエミリーとルークの旅が彼らの関係性において重要なものであることが強調され、前半流れる「Rushes」との対比にも聞こえる。フランクの“brave”という言葉と同時に水に飛び込んでいく二人のカットがこのシーンにおいてはとても象徴的である。
“ This is not my life
It’s just a found farewell to a friend
It’s just a found farewell to a friend
This is not my life
It’s just a found farewell to a friend
It’s not what I’m like
It’s just a found farewell(brave) ” – Seigfried by Frank Ocean
さらに、この映画の大きなインスピレーション元となっているフランク・オーシャンと通ずる部分は曲以外にも見える。例えばこの映画全体のテーマの一つとしてマスキュリニティの問題があると思う。
これは、過度な「男らしくあるべき」という考え方が、時には人のアイデンティティを抑圧してしまう要因にもなることを訴えた社会的な問題だが、今作でもそれが、タイラーと父親の関係を通して描かれる。スターリング・K・ブラウン[iii]演じるタイラーの父親のロナルドは、息子のタイラーに、すべてを完ぺきにこなすようにと過度なプレッシャーをかけタイラー自身の精神を不安定にさせていく。

NYTimes
劇中でロナルドは息子のタイラーに「我々は人の10倍努力しないと成功できない。これはお前のためにすべて言っていることなんだ」というセリフを言う。ここで言われる「俺たちみたいな人間」とは、自分たちが「黒人である」ということであろう。
現代のアメリカ社会に至っても黒人の人々には平等にチャンスが与えられておらず、成功を手にするには人よりも過酷な道をたどらなければならない。こういった社会の状況が、黒人社会にはびこるマスキュリニティの問題と接続していくのだ。
タイラーが苦しめられるこの主題は、フランク・オーシャンのアーティスト性にもかかわってくる。
フランク・オーシャンはゲイをカミングアウトしており、そういった価値観とは反対を行くアイデンティティの持ち主だ。それはヒップホップ畑から出てきて、従来のマスキュリニティ的なラップソングの真逆を行くような、彼のジェンダーを前提とする曲世界の繊細さと内省的な側面にも表れている。
これは例えば、前で名前を出した映画『ムーンライト』にも通ずるものである。この映画の主人公タイラーは、フランク・オーシャンや『ムーンライト』の主人公とは違い、ジェンダー的にはストレートであると思われるが、社会にはびこるマスキュリニティに向き合うという主題は、フランク・オーシャンの曲や『ムーンライト』などのアート作品とつながる現代的なテーマだろう。
この映画においてフランク・オーシャンの曲が流れる場面は勿論、タイラーが髪を金髪に染めピアノに向かう姿を見ると、どうしてもフランク・オーシャンのアーティスト性を連想してしまう。自分自身を抑圧するマスキュリニティに苦しめられるタイラーの物語に、フランク・オーシャンの曲が寄り添うのだ。
こういった部分をはじめとする、現代の優れたアーティストや作品たちと、様々な側面で接続していく『WAVES』は、正に現代の空気感とカルチャーの関係性が内包された作品であるといえるだろう。この映画の要素を占める音楽たちも、一見現代から過去まで年代はバラバラだが、その時代において切実に歌われたラブソングが多い。
ダイナ・ワシントンやエイミー・ワインハウス、レディオヘッドなどの、年代的にリアルタイムでシンクロしないクラシックたちも、この映画においてはその普遍の部分によって現代の若者の物語に響き渡る。優れた作品には普遍性があり、いつの時代も、誰かの心に響くものであるということである。音楽作品の開かれた性質の部分を最大限に生かし、今の若者の繊細で息が詰まるような、絶望と希望の物語を語った『WAVES』は、現代のカルチャーが産み落とした傑作である。
[i] テレンス・マリック:アメリカの映画作家。主な作品に『天国の日々』『ツリー・オブ・ライフ』など。今作の父親のマスキュリニティ的価値観を押し付けられる息子という構図は『ツリー・オブ・ライフ』にも通ずる構図だ。
[ii] ナイン・インチ・ネイルズ:1988年に結成されたアメリカのロックバンド。今年の3月に新作アルバム『GhostsⅤ;Together』と『GhostsⅥ:Locusts』もリリース。
[iii] スターリング・K・ブラウンが今回演じた役は、彼のフィルモグラフィー的にも『アメリカン・クライムストーリー:O・J・シンプソン事件』や『ブラックパンサー』で彼が過去に演じた役にも通ずる。
Writer : 市川 タツキ
RELATED POSTS
NEWS



FEATURE
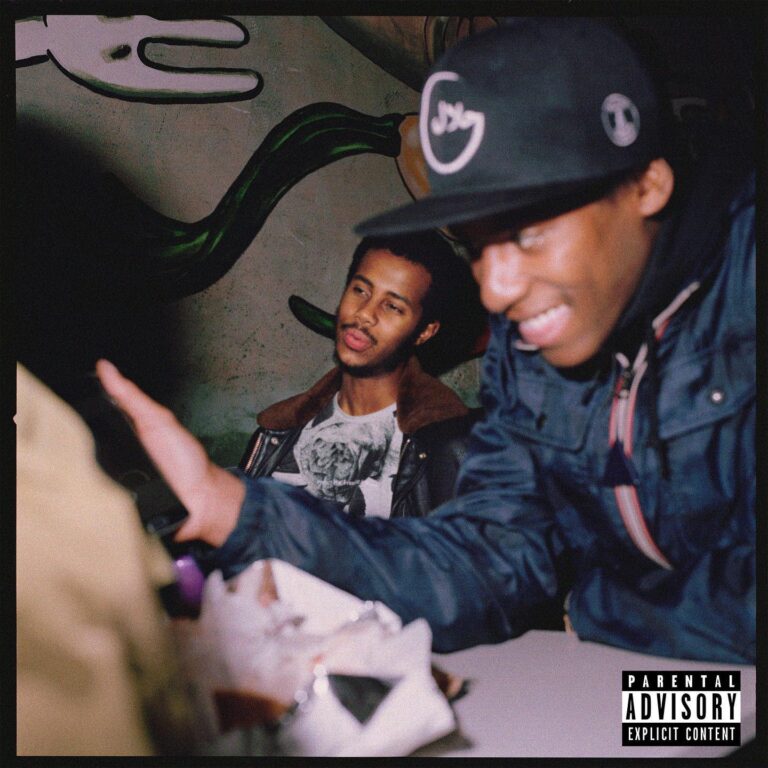

LATEST LYRICS